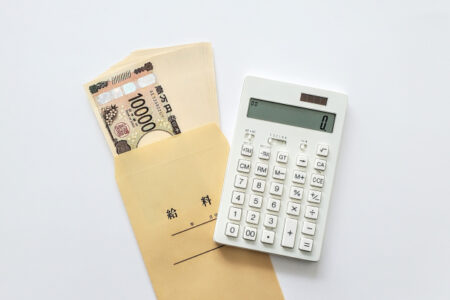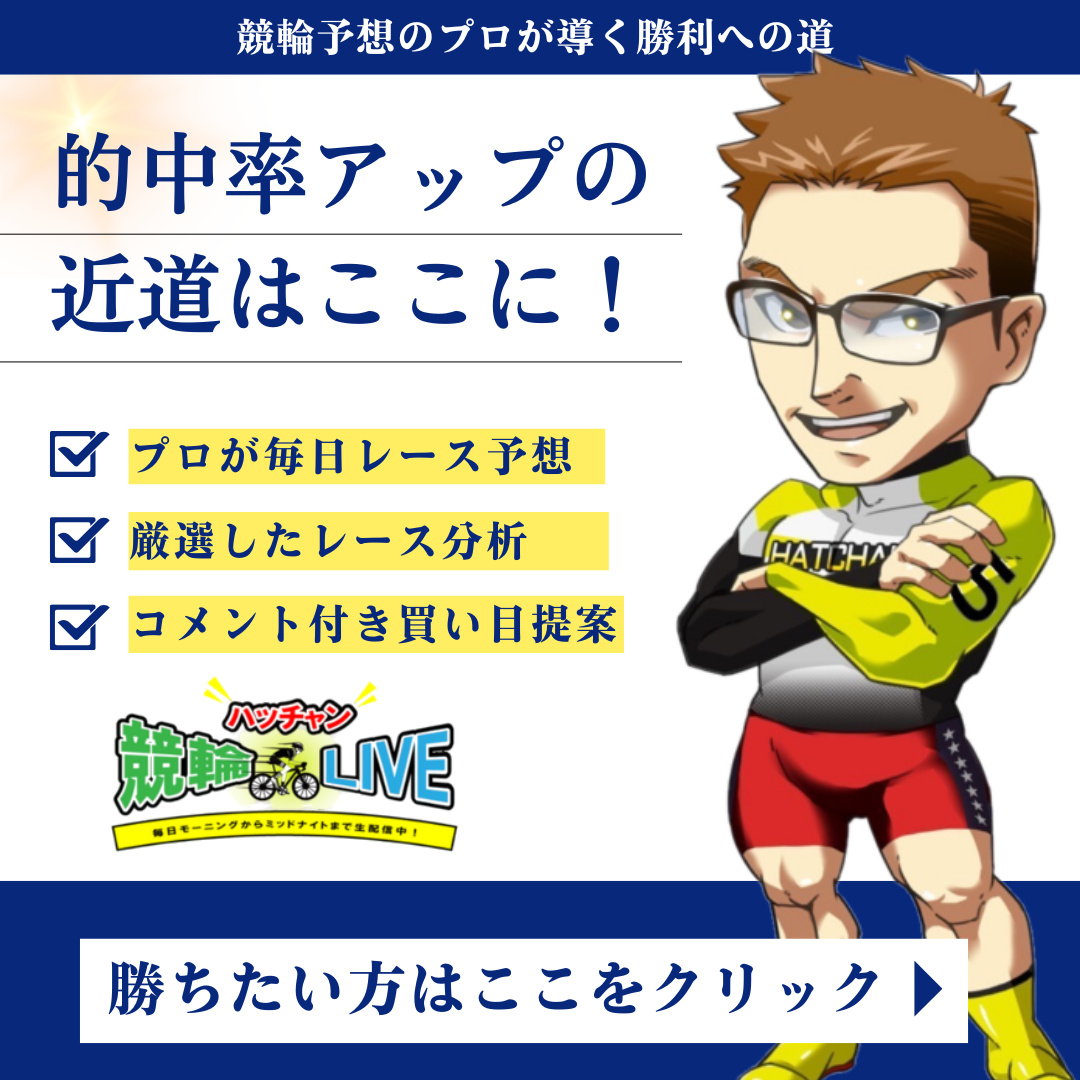ハッチャン競輪ではYouTube配信も行っております。
ぜひチャンネル登録をお願いします!皆さんの応援が配信のエネルギーになります。
↑こちらをクリックしていただくとそれぞれのYouTubeチャンネルに飛びます。
はじめに
競輪は単なるスプリント勝負ではありません。選手個々の戦法やレース展開などで勝負の流れは変わっていきます。
そして、レースの展開を左右する要素のひとつが「ペース配分」です。
スピードを一気に上げるタイミング、力を温存する区間、仕掛けの瞬間――こうした配分の巧拙によって、勝敗は大きく変わります。
特に自力選手にとっては、どのタイミングで仕掛けるか、どれだけ脚を残しておけるかが運命を左右します。
しかし、競輪初心者にとっては、そもそも「ペース配分」とは何なのか、どうやって展開に影響するのかが見えづらいかもしれません。
この記事では、競輪におけるペース配分の基本から、脚質ごとの違い、観戦時の注目ポイントまでを分かりやすく解説します。
1.競輪における「ペース配分」とは何か?
競輪のレースは、誘導員がレース前半を一定のスピードで引っ張ることで、急な駆け引きを避け、安全性と展開の均衡を保つよう設計されています。
選手は誘導員の後ろにつきながら位置取りを図り、残り2周〜1周を目安に一気にレースが動き始めます。
この「誘導員離脱後」こそが本当の戦いの始まりです。
このとき、どのタイミングで仕掛けるか、どのくらいのスピードで踏み続けるかという「配分」が勝敗に直結します。
全力で踏み続けると最後の直線で脚が残らず失速し、逆に温存しすぎると勝機を逃します。
つまり、競輪の「ペース配分」とは、ゴールに向けて体力と脚力をどう使い切るかという“戦略”なのです。

2.ペース配分がレース結果に与える影響とは?
ペース配分を誤れば、どれだけ能力が高い選手でも勝利は遠のきます。
例えば、仕掛けが早すぎてラスト半周でタレてしまうケース、あるいは様子を見すぎてタイミングを逃し、外から被せられてしまうこともあります。
レースは常に相手との駆け引きであり、自分だけのペース配分では勝ちきれません。
また、ラインの前を走る選手の配分次第で、番手・三番手の選手にも影響が出ます。
前が早仕掛けしすぎれば後ろも消耗し、後ろが反応できなければラインが機能不全に陥ります。
つまり、ペース配分は“個人”の問題であると同時に“チーム戦”でもあるのです。絶妙なペース配分が決まったとき、ライン全体が勝機を得る展開になります。

3.脚質・戦法ごとに異なるペース配分の考え方(逃げ・捲り・追込み)
競輪選手は大きく「逃げ」「捲り」「追込み」という脚質に分けられます。
それぞれに求められるペース配分の戦略も異なります。
逃げ型の選手は早めに先頭に立ち、スピードを維持しながら押し切る力が必要。したがって、残り2周から徐々に加速していくようなロングスパート型の配分が求められます。
一方、捲り型の選手は、他選手の動きを見極めつつ、残り1周からの一気の加速を狙います。配分としては中盤まで温存し、短時間に最高速を叩き出す力がカギ。
追込み型はさらに温存型で、最後の直線だけに力を集中させる戦法です。
このように、脚質によって「どこで力を使うか」の設計図が全く違うのです。
4.突っ張り、スロー、ハイペース…展開別のペース配分の実例解説
レース展開によって、選手のペース配分は大きく変化します。
たとえば「突っ張り」と呼ばれる先行争いでは、序盤からハイペースになりがちで、逃げた選手は脚を残す余裕がほとんどありません。こうした展開では、捲り型の選手が体力を温存し、終盤に逆転するチャンスが生まれます。
逆に「スローな流れ」では、先行選手が悠々とペースを握り、後続が動けず苦しむ展開になることも。こうした場合、追込み型の選手が直線一発に賭ける戦略を取る傾向があります。
つまり、ペース配分は「自分の戦法+展開」によって即時に再設計されるもの。
これこそが競輪の奥深さであり、読者が観戦を楽しむポイントでもあります。

5.観戦初心者でも楽しめる!ペース配分の見どころと注目ポイント
競輪観戦初心者にとって、ペース配分を理解するには「残り2周」からの展開に注目するのが効果的です。
特に「打鐘(ジャン)」が鳴った後の動きは、各選手がどのような意図でレースを組み立てているかが最も表れる瞬間です。
仕掛けが早ければ、その選手は逃げタイプ。
中団から急激に上がっていくなら捲り型、終始最後尾でじっとしていた選手が直線で突っ込んでくるなら追込み型です。
それぞれの戦法がどう展開に噛み合うかを観察すると、レースがより立体的に見えてきます。
ペース配分を意識することで、勝敗の伏線に気づく「観る楽しさ」が広がります。
6.おわりに
競輪は、単なる脚力勝負ではなく、スピードを「いつ」「どのように」使うかという戦略性に満ちたスポーツです。
ペース配分を読み解くことで、展開の意図が見え、レースの楽しさが何倍にも膨らみます。
特に脚質ごとの違いや展開別の配分の妙を知ることで、競輪観戦の“玄人感”も味わえるでしょう。
さらに、こうした知識は車券予想にも大いに役立ちます。
もし予想力をさらに磨きたい方は、プロギャンブラー・ハッチャンの競輪予想も参考にしてみてください。
YouTubeチャンネル「ハッチャン競輪ライブ」では、プロの予想師によるライブ実況を視聴できるため、競輪の知識とプロの思考を学ぶことができます。
————————————————————–
そして、より実戦的な買い目やレースごとの狙いどころを知りたい方には、プロギャンブラーハッチャンがnoteで公開している買い目予想が役立ちます。
モーニングからミッドナイトまでの全開催を対象に、プロの独自のデータ解析に基づいて予想をしています。
豊富な経験に基づいたプロの視点を取り入れることで、買い目の見方に自信を持ち、さらに競輪を楽しめるはずです。